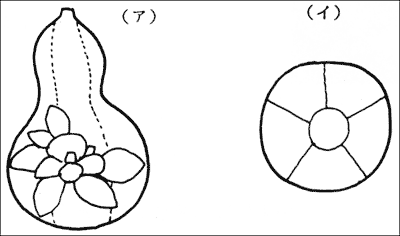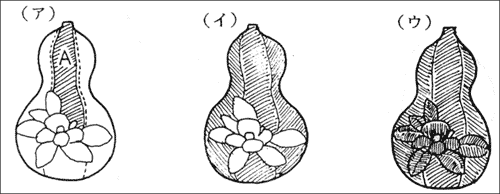|
木目込み(布貼り)(石附 トヨ) |
|||
|
概要 |
瓢面に筋彫りを入れ、布を張り付けていく技法。人形製作での技法を瓢箪に応用したもの。
「木目込み」という名の由来には二通りの説があり、一つは、木の目(節)に衣装を着せていくところからのもので、もう一つは、衣装の人形自体に“きめこむ”ところからの名だという説である。一部では「極め込み」という字を当てているところもある。
| 材料・用具 |
瓢箪、彫刻刀、金べら、布各種、木目込み用ヘラ、木工用ボンド、小皿、小筆、濡れタオル、ハサミ、まち針、そり鋏、絵の具
|
作業手順 |
| 1) | 題材を決める(例:つばき) |
| 2) | 下絵を描く。 |
|
半紙に「つばき」の絵を描き、瓢箪にカーボン紙を当てて絵を複写する(図ア)。瓢箪は丸みがあるので、瓢箪を5等分か6等分し、鉛筆で線を描く。底は縦の線が集まって作業しにくいので、図イ)のように円を描く。
|
|
| 3) | 線に沿って筋彫りをする。 |
| 彫刻刀で幅1mm位、深さ2~3mm位、一定の線になるように筋彫りをする。 木目込む布の厚さによって、幅、深さを変えた方がよい。 |
|
| 4) | 型紙をとる |
| 半紙にとった「つばき」の葉、花弁、めしべ部分を一枚ずつ切り離す。花・葉以外の広い部分は瓢箪に合わせて型紙をとる。 | |
| 5) | 布を裁断する。 |
| 布の上に型紙を載せ、ずれないようにまち針で止める。型紙より1cm位大きめに裁断する。 ただし、瓢箪の丸みの差が大きいところは、布を多めに取った方がよい。特に織りの荒い布や刺繍のある布は、端がほつれやすいので、多めに切っておくとよい。 |
|
| 6) | 布を木目込む |
|
小皿にボンドを取り出し、金べらの先にボンドをつけて、瓢箪に掘った溝の中に入れる(図アの斜線Aの部分)。
|
|
| 7) | 絵の具で線を描く |
| 絵の具を溶かして適当な色をつくり、めしべ、葉脈などを描き入れる。 | |
| 8) | 仕上げ |
| よく木目込んだものでも作業をしている間に布糸が出てくることがあるので、直して完成となる。 |
|
作品例 |