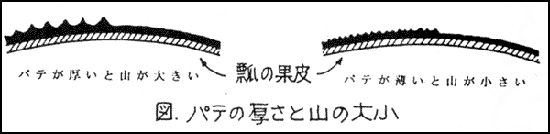|
たたき技法による研ぎ出し(内山 英雄) |
|||
|
概要 |
一般的な研ぎ出し瓢の場合、瓢自体の有する凹凸で模様が出来るが、この場合は、概して大きな模様になる。ここでは、パテを塗ることによって人工的な凹凸を造り、これを土台にして、前ページの研ぎ出しを施す。これにより、細かな模様、意図的な模様を出すことができる。
|
材料・用具 |
一般的な研ぎ出し瓢のところに掲げたものの他、次のものを用意する。
1)パテ 2)こねる容器 3)こねるヘラ(棒)
|
作業手順 |
| 1) | 瓢の口に棒を挿して固定する。 | ||||
| 2) | 粉末のパテに少々水を入れて、耳たぶよりやや軟らかく、よく練る。 | ||||
|
|||||
| 3) | 瓢を持って、よく練ったパテを指の腹につけて瓢の尻の方から順次こすりつけ、指腹で叩くと、粘りがあるから山が出来ていく。同様にして瓢全体に山を作って、スタンドに立てて乾燥を待つ。
|
||||
| 4) | 山の頂上(先端のトンガリ)を落とす。 | ||||
| 320#のヤスリで山の先端をすり落とす(水をつけない。) | |||||
| 5) | 塗装する。 | ||||
| 以下の作業工程は、一般の研ぎ出し瓢に準ずる。 |
|
参考 |
| 1) | パテは表具店、室内装飾店などに発注する(メジトップ60がよい。) |
| 2) | パテの色は、白または黄色が多い。研ぎ出していくと必ずパテが顔を出すので、白または黄色の斑点が出てくる。これを避けるために、練る段階でパテを着色しておいた方がよい。 |
| 3) | 着色は、水溶性のものであれば良い(例 絵の具、茶粉、ベンガラ) |
| 4) | 着色した場合は、この色を「初回の色」として、これ以降の色の順序を考えなければならない。 |
| 5) | 特に最終の色は、着色したパテの色との対比を考えて決める。 |
 |
写真説明:・叩き技法の一次加工 叩き終えたところ。細かな突起を人工的に作ったところ。 |